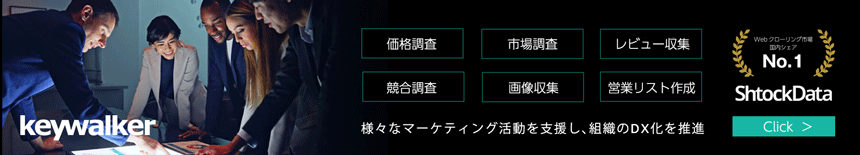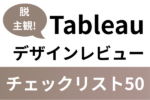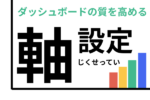データを”見る”から”使いこなす”へ──ユーザー数が4,500名へ増加!現場へ寄り添い伴走するセルフBI推進
導入事例:株式会社アンドエスティHD 様

40を超えるブランドを展開し、国内外で1,500以上の店舗を運営、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)の会員数が2,060万人(7月末時点)を超えるファッション企業である株式会社アンドエスティHDグループ様。現在、社内全体でのセルフBIの実現に向けた取り組みを進めており、これまでに「Tableauダッシュボード作成支援」や「Tableauワークショップ」など、弊社の各種サービスをご活用いただいてきました。
そして今回は、アンドエスティHD様でセルフBIが浸透してきた背景や、なぜ弊社を推進パートナーに選んだのか。そして、現場のメンバーが自ら進んでBIを使うようになるまで、どのようなステップを踏んだのか。データインテリジェンス部の菊池様にお話を伺いました。
アンドエスティHD様のTableauダッシュボード作成事例はこちら
アンドエスティHD様のTableauワークショップ事例はこちら
40を超えるブランドを展開、国内外で1,500以上の店舗を運営
ーーはじめにアンドエスティHD様の事業内容と菊池様の業務内容について
菊池様:
弊社はグローバルワークやローリーズファームなどのファッションブランドにとどまらず、コスメや飲食、雑貨など衣食住に関わるマルチカテゴリーで商品を展開しています。
私が所属しているデータインテリジェンス部では、全社的なデータの利活用を推進しており、その中で私はデータ基盤とBIの領域を担当しています。

様々なブランドにおける帳票統一の限界
ーーセルフBI推進前に業務上課題となっていたこと
菊池様:
現在、弊社が展開するブランド数は40を超えており、それぞれのブランドで重視する指標や見たいデータが異なるため、帳票の統一が難しく、スピーディーな対応ができないという課題がありました。
すべてのブランドに個別対応していては限界があると感じ、各ブランドの担当者が自ら柔軟にデータを分析できるセルフBIの体制を構築したいと考えるようになりましたが、いきなり各自が自由に分析を行うのはハードルが高いため、まずは”社内の誰もが日常的にデータを見る”という文化を根付かせることから取り組みをスタートしました。
ーーセルフBI推進のパートナーにキーウォーカーを選んだ理由
菊池様:
”社内の誰もが日常的にデータを見る”ための施策として、以前、スタッフボードというダッシュボードを作成する案件をキーウォーカーさんに委託したのですが、その際にビジュアライズに関する知見が非常に豊富だと感じ、強く印象に残っていました。
セルフBIを推進していく上で、単に数値を集計するだけでなく、見やすく・わかりやすく可視化することで、現場が効果的に示唆を得られるようにしていきたいと考えており、その点でキーウォーカーさんなら貢献いただけると感じ、セルフBI推進のパートナーとしてお声がけいたしました。
さらに、ビジュアライズのデザインに関するガイドラインをお持ちであることに加え、ワークショップやトレーニングなどの支援メニューも充実していたため、今後のセルフBI推進においても継続的に活用できるのではと考えています。
一緒に悩み、一緒に考える、軌道に乗るまでの伴走がBI推進のキーポイント
ーー現場の方々が“BIを自ら使う”ようになるまでの施策や工夫、エピソードなど
菊池様:
トレーニングで操作方法を学んだとしても、多くの社員が「何から始めればよいか分からない」という状態でした。そこで、各ブランドごとに「データから何を知りたいのか」「何を変えていきたいか」といった観点でヒアリングを行い、伴走しながら一緒に要件を整理していきました。
一度伴走することで、担当者が主体的にアクションできるようになっていきましたので、単に環境を用意するだけでなく、軌道に乗るまでの伴走がセルフBI推進において非常に重要だと実感しました。
私自身も最初は手探りでしたが、取り組みが進むに連れてナレッジが蓄積され「他のブランドではこういった課題もあり、このように活用していました」というように横展開できるようになってきました。
今後新たにメンバーが加わっても躊躇なくBIを活用していけるよう、これからはナレッジマネジメントにも力を入れ、BIに対するハードルを下げていきたいと考えています。

ーーセルフBIが浸透してきた結果、ユーザー数や分析頻度などの観点から前回のダッシュボード導入時と比較しての変化
菊池様:
セルフBIの取り組みが浸透してきたことで、前回のダッシュボード導入時と比べて大きな変化があり、ユーザー数は約4,500名と、当時の約2倍にまで増加しています。そのうち約200名は「Explorer」の権限を持ち、自由にデータ分析ができるユーザーとして日常的に活用してくれています。
さらに特徴的なのは、こちらから声をかけなくても「自分もやってみたい」と能動的に手を挙げてくれる方が増えてきた点です。こうした“ボトムアップ”の広がりは非常に心強く、現場に浸透してきた実感があります。
一方で、すべてが順調に進んだわけではなく、全員がBI活用から離脱してしまったブランドもありました。そのような場合には、他ブランドでの成功事例をブランド長に共有し、理解と納得を得ながら“トップダウン”で巻き込むことも重要だと感じています。ですが、押し付けにならないよう、きちんとメリットを伝えた上で進めていくことが必要だと考えています。
また、情報共有の取り組みとして、今年の3月から社内報をスタートし、毎月1回、ユーザーがパブリッシュしたダッシュボードの事例紹介を行っています。こうした取り組みが今後のさらなる活用促進につながると考えています。
毎週40〜60時間分の業務を削減
ーーセルフBIによる定量的/定性的なメリットについて
菊池様:
定量面での大きなメリットは業務の効率化です。例えば、毎週行われるブランド別の報告会議に向けた資料作成では、これまで、データを抽出し加工する作業が1ブランドあたり2〜3時間かかっていたのですが、セルフBIにより大幅に短縮され、作業も簡易的になりました。20ブランド分となると、それだけで全社で毎週40〜60時間分の業務が削減された計算になります。
定性面では、削減できた時間を他の業務にあてたり、データ分析をより深く入念に行ったりできるようになっています。
立ち上げ期から現場に寄り添う柔軟な支援が心強い
ーーキーウォーカーの評価(支援体制全体や研修内容、フォローアップ、QA体制など)について
菊池様:
特に立ち上げのタイミングで非常に手厚い支援をしていただき、ありがたかったと感じています。中でも印象的だったのは、トレーニング内容を弊社の状況に合わせて柔軟にカスタマイズしていただいたことです。実際の自社データや業務シナリオに即した内容に修正してもらえたことで、受講者の理解度も高く、実務に直結した学びが得られました。
また、現在も引き続きユーザーとの密なコミュニケーションをとっていただいている点も非常に良いと感じています。ユーザーの声に耳を傾けながら支援していただけていることで、安心感があります。
今は「もっとアクティブユーザーを増やしていきたい」というフェーズに入っているので、そうした次のステップに向けたアイデアを、ユーザーとの日々のやりとりを通じて汲み取り、提案いただけることを期待しています。
全社横断で進めるデータカルチャーの定着と人材育成
ーー今後の展望について
菊池様:
今後の展望としては、全社的にデータ活用をさらに広げていくことを考えています。現在は、セルフBI参加者全員が我々と繋がっている状態ですが、効率的なコミュニケーションやブランド内の運用強化も見据え、各ブランドにCoEとなる方を配置して体制の最適化を進めたいと思っています。
今はまだトライアル中なこともありますが、全社で定着化できるように推進を強化していきたいと考えています。
さらに今後は、これまであまり手をつけられていなかったコーポレート部門や、新たにグループに加わった企業などにもセルフBIの取り組みを広げていきたいと考えています。
また、データ活用の広がりに合わせて重要になるのが人材育成です。単にツールを使える人を増やすだけでなく、「なぜデータを見るのか」「どう活かすのか」といったデータカルチャーの浸透にも力を入れていきたいと考えています。
ーーこの度はお時間頂きありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。